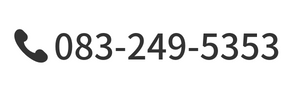早速届いたばかりの器にデビューしてもらった。

(*・ω・)(*-ω-)(*・ω・)(*-ω-)ウンウン♪
なかなかいいかんじ♡
整ってないというか型に納まってないというか、バランスセットとの対比ができてる感じ。
今回のチョイスは一応は成功?と言えると思う。
ところで。
近頃何やら、3NASび店舗の隣の隣が活発な動きをしているので、気になって様子を見に行ったところ…。

スゴッΣ(・ω・ノ)ノ!
カウンターテーブルを作成中だったのだがこれがなんと!カット&塗装した木材をひとつひとつ組み上げっていってて…まさに唯一無二なものが完成しようとしていた。
どんなお店ができるのか聞くところによると、単純にテナントとして貸し出すのではなく、いろんな役割(どんな役割か聞いたのだが、個々では省略)を担った多目的なカフェバーにする予定とのこと。
このカウンターテーブルひとつとっても計画が壮大過ぎて、期待の反面不安も…。

だってこれ、掃除が大変そうすぎる(@_@)主婦目線。
一気に大きく進めるのもすごいことだとは思うけど、思うようにいかなかった時に改変しやすい余白を残しておくことも必要な気がする。
だって、今までほかの人がやってなかったことをしようとするんだから、計画通りにいかないことは当然あるわけで、その時「変える」余白はある程度必要だと思う。
ほかの地域では実施済みでも(そこでは成功したとしても)、下関の茶山通りでも同じようにいくとは限らないし。っていうかむしろ、同じようにならない可能性の方が…(-_-;)。
その点、3NASびはいまだにtry&errorを繰り返して、少しずつ変化中。
これは諸事情(主に金銭的事情)で授業として大きく進めることができないという理由もあるが、この場所で続けることでわかってきたことに対応して変化させていくことの必要性に気づいたからで。
きっちりつくり込んで大きく進めるのなら、むしろ事前にもっと深く「地域性」的なものをリサーチしておく必要があるのでは…?と。
やろうとしていることはもちろん素晴らしいと思うし、協力・応援できたらと思ってはいるのだけれど、成功しそうかどうかというと…うぅ~…ん…(-_-;)である。
下関の官民巻き込んでの動きはもちろんすごいし、下関以外の自治体と交流しての動きも目を見張るものがある。けれど…。
どうにも「茶山通り」にハマってない気がしてならないのだ。
ほかの自治体や地域と地理的条件などが同じだとしても、県民性というか市民性というか地域民性というか、そこで暮らす「ひと」にハマってない感じがするのだ。
まぁこれは何か明確な根拠があるわけではなく、この地で約3年半お店を営業したことで感じる肌感みたいなものなのだが。
とりあえず「うまくいかなくても2年は続ける」ことが最低限必要だと思う。
やり始めたらいろいろと思ってたのと違うところが出てくるだろう(むしろ思った通りに行くことの方が少ないかも?)。
それらに対応させて変化させながらでも、とにかく続けることがこの場所での信頼獲得(からの更なる発展)につながる方法だと。今の私は思う。
理想を描いてスタートするのはめちゃくちゃ素敵なこと。
けれど、そこに「変わる」適応力と「続ける」忍耐力が必要で。
50年かけて廃れていった地域を再興させるのは………