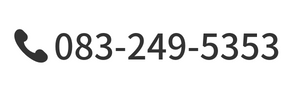ここ最近、今まで以上に料理をするのが楽しくて仕方がない。
いろんな食材や調理方法に出会うことで、料理というものの自由度が増していってるからだろう。
お客様から、料理や食材や調理方法などについての質問をされることもよくあるのだが、「企業秘密」なんてことはなく、基本すべてオープン。
より多くの人に料理を楽しんでほしいし、(お魚はもちろん)いろんなものを食べてほしいと思うからだ。
献立やレシピはどうやって考えてるの?という質問もよくもらうが、これに関しては「パズルの組み立て」。
献立は「食材×味付け×調理法」で、1日のメニューの中でできるだけかぶらないように組み立てていく(たま~に変なピースが入ることも(;’∀’))。
レシピは「メイン食材×サブ食材×調理法×基本調味料×アクセント調味料」。
「メイン食材×サブ食材」とは…。
例えば胡瓜の酢の物の場合、当然メインは胡瓜。
それに、大根・わかめ・人参・キャベツ・(大葉などの)薬味野菜、(小海老やアサリなどの)魚介類、(蒸し鶏などの)肉類を加える。
サブ食材は複数合わせることもできる。
「アクセント調味料」とは…。
例えば酢の物をつくる際、基本の和え酢の配合は決まっているのだが、食材によって酸味を強めにしたり甘めにしたり、旨味(出汁)を足したり。
そこにさらに梅・柚子・レモン・生姜・味噌・胡麻などを加えることで変化をつけるのだ。
これらの掛け算によって、無限大にレシピは増える。
後はこの掛け算が思いつくかどうかだけ。
私の場合、基本的にこの掛け算は頭の中でのみ考えられる。
実際に試作して試食して改良して…という工程はほとんどしない。
かなり驚かれるが、日々の料理も調理中の計量もしなければ、ほとんど味見もしない。
頭の中でほぼほぼ仕上がってるからだ。
食材の持つ微妙な水分や油分、(特に魚介類は)塩味や旨味の違いによって多少のブレはあるものの、そう大きく外れることはない。
なので味見するのは料理ではなく、その前段階の食材そのものや調味料の方かな?
とはいえ、初めからこうだったわけではない。
昔は当たり前にレシピを見ながら計量しながら料理して、それを試食をして調整して…としていた。
では、いつから今のスタイルになったかと言えば、とある加工食品の製造会社で、品質管理&商品開発部門で、配合案の作成・試作を担うようになってからだ。
取り寄せた食材や副資材(調味料や添加物)のサンプルを用いて試作品をつくるのだが、「どの食材・調味料を組み合わせるか?」「その配合割合はどうするか?」(に加え「作業工程は現場でも可能なものか?」「原価率はどうなのか?」なども)すべてを実際に試作することは物理的に不可能で…。
サンプルそのものとその資料を基にある程度頭の中で組み立てて決め打ちしてからの改良(この改良も頭の中で組み立ててからの決め打ち)。
これを毎日毎日繰り返すことで、実際につくらずとも頭の中で完成形がつくれるようになってきた。
うま味調味料や甘味料や香料など、耳かき半杯で味が激変するものを扱ってたので、(醤油や砂糖や酢など)通常の調味料なんてお茶の子さいさい( ̄ー ̄)ニヤリ。
計量に関しても然り。
0.01グラム単位での計量(現場の200分の1くらいのスケールで試作するので)を繰り返していたので、塩一粒の粒子の大きさでその重量がわかるようになった。
味見に関しては、「味覚」よりも「視覚」や「嗅覚」「触覚」の方が重量で。
そんなこんなで今に至るわけだが、ここへきて自分の成長を感じる今日この頃。
新しい食材との出会いがアイデアを増やしてくれる。
そのうえで、頭の中と実際の料理のドンピシャ率の精度が上がってる。むしろ頭の中以上のものが出来上がることも多々。
もっともっといろんなものと出会いたい。
もっともっといろんなものをつくりたい。
もっともっといろんなものを届けたい。
これからの3NASびにも、乞うご期待!だ(*´▽`*)。
余談
何人かの人から「レシピ本をつくってほしい(≧◇≦)」と言われたのだが、私の料理はあまりに感覚的過ぎて、レシピ本つくったとしても滝沢カレンさんのみたいになると思うので、お役に立てるかどうか…(^^;)だ。